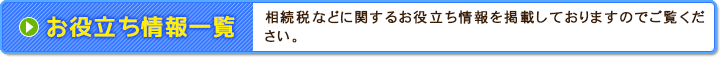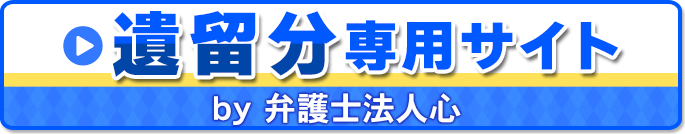相続税の申告をすると必ず税務調査が行われますか?
税務調査とはどのようなものですか?
税務調査とはどのようなものですか?税務調査とは、申告内容に誤りがないか税務署が確認する調査手続きのことをいいます。
相続税の税務調査の多くは、納税者が相続税の申告書を提出した1から2年後の、8月から11月頃に行われます。
申告書を提出してから3年目以降に実施される場合もありますが、年数が経つにつれ調査確率が減少する傾向があります。
なお、相続税の法定申告期限から5年が経過すると、相続税の時効を迎えるため、それ以降は税務調査が行われないのが原則です。
ただし、相続財産隠しなど不正行為によって税額を減らしていたことなどが発覚すれば、時効期間は7年まで延長されます。
税務調査の対象になりやすい人はどのような人ですか?
税務調査の対象になりやすい人はどのような人ですか?統計によれば、相続税の税務調査の対象になる割合は、納税者の5人に1人程度と言われています。
そして、納税者のうち、以下のいずれかに当てはまる人は、税務調査の対象になりやすいと言われています。
⑴ 申告書に不備がある人
申告書の内容に不備があると税務調査が入る可能性が高くなります。
税務署は、亡くなった被相続人の預貯金や不動産など、財産とお金の流れを細かく把握していますので、その内容と申告された相続財産に違いがあれば、ミスや財産隠しを疑われます。
⑵ 多額の納税額がある人
相続財産が多額だと、それだけミスや見逃しのリスクが増えます。
また、単純な計算ミスだけでなく、不動産や有価証券、美術品や宝飾品などの評価ミス、財産の見落とし、悪質な場合は意図的な財産隠しも疑われる可能性があります。
⑶ 金融資産を多く相続した人
相続財産に不動産が多い場合に比べて、預貯金等の金融資産が多い場合の方が、税務調査を受ける可能性は高いと言われています。
不動産は評価額の算定が複雑なため、税務調査の際に「解釈の違い」が焦点になりやすく、明確な申告漏れを指摘しにくい傾向があります。
それと比べると、金融資産の場合は金額がはっきりしており、明確な申告漏れを見つけやすいのです。
⑷ 税理士に依頼せずに相続税の申告をした人
税理士の資格を持たない人が、税理士に依頼することなく申告した場合、調査対象になりやすい傾向があります。
税理士資格を持たない人が関与せず申告した書類は、誤りがあってもおかしくないと判断される可能性があるからです。
⑸ 相続税の申告をしていない人
税務署は、所得税の申告書などから賃貸物件や不動産を持っていることを把握しています。
それらがあるにもかかわらず、相続税の申告をしていない場合は税務調査を受ける可能性が高くなります。
相続税の2割加算に関するQ&A 養子縁組が相続税対策となるのはなぜですか?