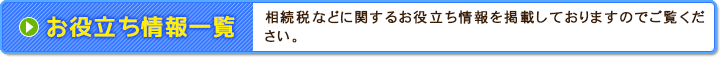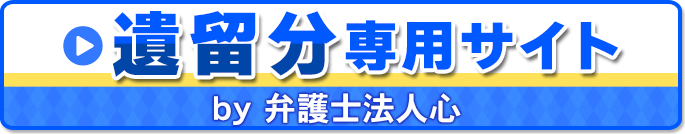養子縁組が相続税対策となるのはなぜですか?
1 養子縁組による相続税対策
親が子の配偶者や孫など、実子以外の人を養子に取る養子縁組をすることで、相続税対策をすることができます。
もっとも、相続税の節税のために養子縁組をしたことにより、遺産分割の際に、実子との間で揉めてしまう可能性がありますので注意が必要です。
2 相続税の非課税枠を増やすことができます
養子縁組をすることが相続税対策になるのは、まず、相続税の基礎控除を増やすことができるからです。
相続税は、被相続人の財産の総額から基礎控除額を控除した金額に課税されます。
そして、相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」とされています。
ここで、被相続人が養子を取ると、法定相続人が増えることになります。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額が増え、相続税の非課税枠も増えていくことになります。
また、被相続人の財産が相続税の基礎控除額の範囲内になれば、相続税の申告をする必要もなくなります。
もっとも、相続税の基礎控除額の計算に組み入れる場合、法定相続人の数に入れることができる養子の数には制限があります。
基礎控除額の計算に組み入れることができるのは、被相続人に実子がいない場合は2名まで、被相続人に実子がいる場合は1名までに、それぞれ限定されています。
3 生命保険金の非課税枠を増やすことができます
また、養子縁組をすることで、相続が発生したときの生命保険金の非課税枠を増やすこともできます。
生命保険金にも相続税が課税されますが、一方で、非課税枠も設定されています。
生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」とされています。
ここでも、被相続人が養子を取ると、法定相続人が増え、それによって、生命保険金の非課税枠も増えていくことになります。
もっとも、生命保険金の非課税枠の計算についても、相続税の基礎控除額の計算と同じように、法定相続人の数に入れることができる養子の数に制限があります。
相続税の申告をすると必ず税務調査が行われますか? マンションを相続した場合の小規模宅地等の特例についてのQ&A