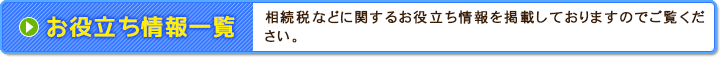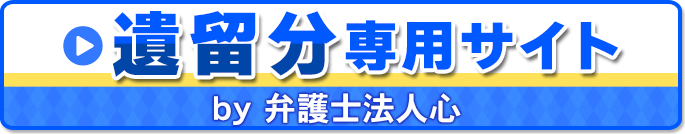小規模宅地等の特例に関するQ&A
小規模宅地等の特例を使うと、なぜ相続税が軽くなるのですか?
遺産の総額を大幅に減らすことができるからです。
相続税は、遺産の総額がいくらなのかによって、決定されます。
遺産が多いほど、相続税の額も大きくなっていきます。
たとえば、遺産の総額が9000万円の場合と3億円の場合を比較すると、他の条件が同じであれば、当然遺産の総額が3億円のケースの方が相続税額が高くなります。
反対に、遺産が少ないほど、相続税の額は少なくなります。
ここでいう遺産には、預貯金などの金融資産はもちろん、不動産も含まれます。
もし、比較的高額な財産である土地の評価額を下げることができれば、どうなるでしょうか。
たとえば、本来は8000万円の価値がある土地があった場合に、この土地を3000万円の価値だと評価できれば、遺産総額は5000万円下がることになります。
遺産総額が下がれば、相続税も軽くなります。
これを実現するのが、小規模宅地等の特例制度です。
なぜ小規模宅地等の特例制度が作られたのですか?
土地を相続できなくなる事態を防ぐためです。
土地は、比較的高額な財産であるため、遺産の中の大部分を占めるという事態が少なくありません。
たとえばお父さんが亡くなり、遺産総額が9000万円で、そのうち土地が7000万円という場合は、どうなるでしょうか。
その土地の上には建物が建っており、お父さんと長女はずっと一緒に暮らしていました。
お父さんが亡くなった後も、長女は引き続きその家に住みたいと考えるでしょう。
そこで、長女がその土地と建物を相続するという形をとった場合、長女は、ほとんどの遺産を相続することになるため、他の相続人にお金を支払うことで調整をするケースが少なくありません。
それに加えて相続税も支払うとなれば、長女のお金が足りなくなり、結果として不動産を売却せざるを得なくなります。
しかし、長女にとってはその自宅はまさに生活の基盤であり、これを失うと今後の生活が厳しいものになります。
そういった事態を防ぐために、小規模宅地等の特例制度が作られました。
300坪の土地を相続しましたが、小規模宅地等の特例は使えますか?
一定の範囲では使うことができます。
小規模宅地等の特例を使うためには、一定の条件があります。
その中の1つに、土地の面積があります。
たとえば、亡くなった方が住んでいた土地に小規模宅地等の特例を使う場合、最大で100坪までしか評価額を下げることはできません。
その他、対象の土地が事業用の土地の場合や賃貸用の土地だった場合は、対象面積が変わってきます。
小規模宅地等の特例には、どんな種類があるのですか?
小規模宅地等の特例には、4つの種類があります。
1つ目は、特定居住用宅地と言われるもので、亡くなった方が居住していた土地に関する特例です。
2つ目は、特定事業用宅地と言われるもので、亡くなった方が営んでいたお店の建物が建っている土地に関する特例です。
3つ目は、特定同族会社事業用宅地と言われるもので、土地の上に亡くなった方が経営していた会社がある場合の特例です。
4つ目は、貸付事業用宅地と言われるもので、亡くなった方が土地を賃貸していた場合の特例です。
相続税の配偶者控除に関するQ&A 相続税の非課税財産に関するQ&A