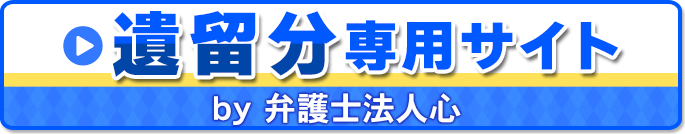「相続税の制度」に関するお役立ち情報
ビットコインなどの仮想通貨は相続税の対象となるのか
1 仮想通貨は相続税の対象となる
仮想通貨は相続財産として、相続税の対象となります。
仮想通貨を含めた相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となります。
2 相続時に売却すると所得税もかかる
仮想通貨の売却益は「雑所得」に区分され、給与や家賃収入などと合算して「総合課税」とされています。
総合課税の所得税は累進課税で、所得が多いほど最高税率が高くなるため、相続税と所得税・住民税でかえって赤字になってしまうこともあります。
この点は、税制改正により課税方法が変わる可能性があるので、動向を注視するのがよいでしょう。
3 仮想通貨とは何か
亡くなった方が仮想通貨を保有していても、相続人は亡くなった方の財産をよく把握しておらず、とりわけ仮想通貨自体になじみがないということも少なくありません。
そのため、念のため以下に概要をお伝えします。
仮想通貨は、令和2年の法改正により「暗号資産」という呼び方になっています。
日本銀行によると、「暗号資産(仮想通貨)」は、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、次の性質を持つものとされています。
① 不特定の者に対して、代金の支払等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。
② 電子的に記録され、移転できる。
③ 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない。
代表的な暗号資産(仮想通貨)としては、ビットコインやイーサリアム、リップルなどがあります。
4 暗号資産(仮想通貨)の相続手続き
亡くなった方が暗号資産(仮想通貨)を保有していた場合、通常の相続手続きと同様に、暗号資産取扱業者に連絡して、遺言書による方法か、相続人全員で遺産分割協議により、手続きを行うことになります。
国内で取引されたものであれば、相続手続きは、銀行の預貯金や有価証券とほぼ同じです。
相続人が亡くなった方の暗号資産(仮想通貨)の存在や暗号資産取扱業者を知らなくとも、相続税の課税対象になってしまいます。
また、海外に口座がある場合には、相続手続きの負担がより大きくなってしまうので、相続人のことを思えば、このようなことも考慮して、タイミングをみて現金化しておくこともよいでしょう。
5 相続した暗号資産(仮想通貨)の評価方法
相続において、暗号資産(仮想通貨)を日本円に換算して支払われた場合、日本円に換算して評価します。
その際、相続開始日の時価で評価します。
日本円での換算時に利益が出ていれば所得税の確定申告も必要となります。
また、被相続人が亡くなった年に暗号資産(仮想通貨)を売却していた場合は、準確定申告が必要となる場合もあります。
いずれにしても税金のことを念頭においておく必要があるでしょう。