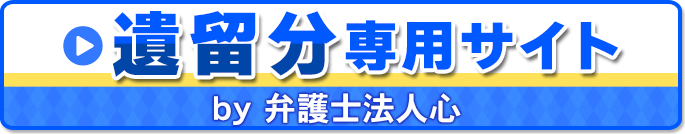「相続税対策」に関するお役立ち情報
生命保険で相続税対策
1 生命保険金は一定額まで非課税にできる
一般的に、生命保険金は受取人の財産であるため相続財産とはみなされませんが、相続税の申告上は遺産ということになり、相続税の課税対象になります。
とはいえ、生命保険金は、一定額まで非課税ということになっています。
つまり、預貯金で持っていれば相続税が課税されるケースでも、生命保険金に変えてしまえば、その部分については相続税が課税されないことになり、それだけ相続税の負担を軽くすることができます。
具体的には、「法定相続人の人数×500万円」が非課税になります。
例えば、相続人が配偶者、長男、二男の3名であれば1500万円までは、生命保険金が非課税になります。
このように、生命保険を活用すれば、相続税の負担を軽減できるという意味で、相続税対策になります。
2 相続税の納付に役立つ
相続税の納付には、10か月という期限があります。
通常であれば、遺産である預貯金を解約し、相続税を納付すればいいということになります。
しかし、相続人全員の同意がなければ、預貯金の解約ができないため、預貯金の解約が難しい場合があります。
例えば、相続人の中に、認知症の方がいる、入院中の方がいる、海外在住の方がいるといったケースだと、相続人全員の同意を取り付け、印鑑登録証明書を銀行に提出するということが難しいかもしれません。
さらに、相続人同士で遺産の分け方で揉めてしまった場合も、預貯金の解約は難しくなります。
しかし、生命保険金は、受取人が単独で請求できるため、他の相続人の同意は必要ありません。
そのため、受取人が生命保険金を受け取り、相続税の納付をすることにしておけば、期限内に相続税を納付することが容易になります。
3 どのような生命保険が適切かは、税理士にご相談を
生命保険契約は、保険契約者、被保険者、受取人といった、聴きなれない言葉がたくさん出てきます。
また、生命保険契約の目的や、家族構成によって、どのようなタイプの生命保険に加入すべきかが異なってきます。
相続税対策という観点から生命保険に加入する場合は、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。